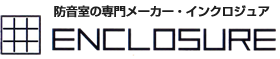無響室か半無響室か?用途別で選ぶ防音空間
1. 無響室とは?
無響室(または無響音室)は、内部の音波がほぼ完全に吸収され、反射音がほとんど存在しない特別な空間です。音がまるで消えたように静かな環境を提供し、自由音場が成立する場所として使われます。無響室の主な用途は、小型音源や特定の設置条件がない音源の測定です。
無響室には以下のようなタイプがあります:
コンクリート遮音型:遮音性は高いものの、低周波振動に弱く、振動伝搬のリスクが高い。また、設置には建物にピットを掘る必要があり、移設が難しい。
パネル組立型:現在の主流。組立・解体が簡単で、移設も可能。従来のコンクリート型のデメリットを克服し、コスト効率も高い。
木+ボード+ベニヤ板型:コストを抑えるための方法ですが、燃えやすい材質のため、安全面で不利です。また、移設は事実上不可能です。
無響室を設計する際には、遮音量、作業効率、暗騒音、測定周波数帯を考慮することが非常に重要です。これらの要素が適切に組み合わさることで、高品質な測定環境が実現します。
2. 半無響室とは?
半無響室は、無響室と似ていますが、床など一部の面が反射する構造です。床や一部の境界面で音が反射し、その上で音が測定されるため、「半自由音場」が成立します。通常、重い機械や床に固定された音源の測定に使用され、反射面を持つ音源に対して適しています。
半無響室も、無響室と同等の高い遮音性能が求められます。床面にはコンクリートなどの硬くてフラットな素材を使い、音波が振動によって反射しないよう十分な配慮が必要です。振動による影響を避けるため、音響環境を慎重に設計することが肝要です。
3. 音響パワーレベルとは?
音響パワーレベルは、機械や装置が発する騒音を評価するための基本的な指標です。この指標は、音源から放射される全体の音エネルギー(音響パワー)を示し、特に機械騒音の評価や騒音予測に多く使われます。音響パワーレベルの測定には、国際規格(ISO 3745など)に基づいた方法が採用されます。
・機械騒音の低減効果の評価
・機械の発注・検収時の騒音評価
・騒音予測に基づいた対策の基本データとして重要
音響パワーレベルは、音源の性能を把握するための基本的なデータとして使用され、精密な測定環境が求められるため、無響室や半無響室が最適です。
4. 音圧レベルの距離減衰特性
無響室や半無響室では、音源からの距離が2倍になるごとに音圧レベルが6dB(A)減少する「逆二乗則」が適用されます。音源から放たれる音の強さが、距離に応じてどれだけ弱くなるかを正確に測定するため、この特性を守ることが重要です。
無響室の許容最大偏差:100Hz~125Hzで±1.5、1KHz~5KHzで±1.0など
半無響室の許容最大偏差:同じ条件で±2.5、±2.0など
これらの基準に従って、音響特性の測定が行われます。
5. 測定方法
無響室では、測定対象音源を囲むように測定球面(球状)を設定します。測定の中心は音源の音響中心と一致させ、半径は音源の最大寸法の2倍以上、最低でも1メートル以上の距離を保つ必要があります。
半無響室では、反射面を基準に**測定半球面(ドーム型)**を設定し、同様に音源の中心から距離を取って測定します。これにより、音の正確な評価が可能となります。
6. 暗騒音の補正
測定時に周囲のノイズ(暗騒音)や測定機器の雑音が影響を与えないよう、音源作動時と停止時の音圧レベルの差が15dB(A)以上あることが理想です。もし、その差が6dB(A)~15dB(A)の間であれば、暗騒音を補正しなければなりません。6dB(A)未満の場合、測定は不可能とされます。
7. 反射を防ぐ工夫
無響室や半無響室では、音波が反射しないように徹底した設計が必要です。例えば、鉄格子の床や機器移動用のクレーンなどは、音波の反射源となり、測定に影響を及ぼします。そのため、測定時には不要な設備を取り除き、吸音処理を施すことが重要です。
また、意外に見落とされがちなのが照明です。蛍光灯は雑音の原因になるため、暗騒音に影響しない白熱灯を使用することが推奨されます。その他、配線ノイズなどにも注意が必要です。
無響室と半無響室を活用して、精密な音響測定を実現!
無響室や半無響室は、それぞれの特徴を活かして、様々な音響測定に最適な環境を提供します。反射を抑えた静寂の空間で、正確なデータを手に入れ、より高度な騒音評価や対策を行いましょう!