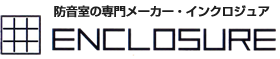人体は“吸音材”?
―コンサートホールと無響室に見る、音と人間の関係性―
音響設計の現場では、「人間の体」もまた空間に影響を与える要素として扱われています。
本記事では、人体の持つ音響的な特性、特に「音の吸収」に着目し、コンサートホールや無響室の設計においてそれがどのように考慮されているかを解説します。
人の体は中高音をよく吸収する
人間の体は、一般に500 Hz〜 5,000 Hzの周波数帯域において、音を比較的よく吸収します。これは、体の大部分が水分を多く含む柔らかい組織で構成されており、音波のエネルギーを熱に変換しやすいためです。
また、着衣(衣服)も音の吸収に大きく関与します。特にウールやフリース、コットンなどの繊維素材は、高音域で音を拡散・吸収しやすく、人が衣服を着ている状態では吸音効果がさらに高まります。つまり、コンサートホールなどでは「人間+服」が一体となって吸音材のように機能するのです。
この中高音域は、会話や多くの楽器の音が含まれる帯域であり、音響空間において非常に重要です。そのため、人が空間内に存在するかどうかで、音の響きや音圧レベルに顕著な変化が生じることがあります。
コンサートホールでは「人の存在を前提」に設計する
コンサートホールの音響設計では、満席時の音響状態を前提として設計が行われます。観客が着席することで、中高音が吸収され、音場の特性が変化するためです。1人なら影響はそこまでありませんが、大人数となると音響、聴こえ等に影響が出ます。
この影響を補うために、ホールの座席には人の体と同等の吸音性を持つ材料が使用されており、空席でも一定の音響性能が保たれるよう配慮されています。また、設計段階ではシミュレーションや頭部トルソー型マネキンなどを用いて、人体の音響特性を再現し、音の拡がりや残響の変化を予測する手法も用いられます。
無響室では「人の存在が誤差」になる
一方で、無響室では人の存在が測定誤差につながるため、設計と運用においては極力人の影響を排除します。
特に、音響機器の評価や車両開発で使用される無響室(例:VSACやEAAC)では、ISO規格(ISO 3745, ISO 3744等)に基づき、逆二乗則が成立する精密な自由音場が求められます。この条件下では、人が室内に入ることで、音圧レベルが0.5〜1.5 dB程度低下することがあり、測定結果に影響を与えます。
そのため、無響室では、室内に人がいない状態での音響測定が基本です。(測定器は室外にセットし、室内のマイクフロフォンで受音するなど)
高周波域では反射が支配的に
人体は中高音を吸収しますが、周波数がさらに高くなると(たとえば超音波領域)、音波は皮膚や着用物で反射されやすくなります。このため、超音波センサーなどの評価においては、反射体としての人体の特性も考慮され、ダミーボディの使用や無人状態での評価が行われます。
まとめ:人間の音響特性を設計に活かす
コンサートホールでは、「人がいて完成する音響空間」を前提に音が設計されます。一方、無響室では「人の存在を排除した正確な音響評価環境」を構築します。
同じ音の空間でも、人間の音響特性(EQ特性)をどう扱うかによって、設計方針が大きく異なるのです。
音響評価の現場では、こうした人体の特性まで含めて計算された設計が必要とされています。これにより、空間そのものが目的に応じて最適化された「音響システム」として機能します。