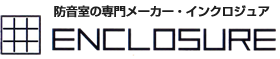聴力検査室の遮音設計5つのポイント ─ 構造・材料・空調まで押さえるべき実践ガイド ─

はじめに|遮音設計の違いが「検査の信頼性」を左右する
聴力検査室に求められる遮音性能は、一般的な静音空間とは異なり、医療レベルの「沈黙」に近い環境です。
特に純音聴力検査や補聴器適合検査などでは、20〜30dB SPL以下の静けさが必要となり、音響設計の質が検査の信頼性を大きく左右します。
この記事では、聴力検査室の遮音設計において重要な5つの実践ポイントを、構造・材料・空調・施工面に分けて解説します。
1. ソラメタパネルによる遮音構造|高性能×薄型を両立
遮音構造の中核を担うのが、**ソノーラテクノロジー株式会社製の「ソラメタパネル」**です。
- 独自の高比重積層構造により、D-50〜D-60相当の遮音性能を、わずか数cmの厚みで実現
- 一般的な石膏ボード多層構造に比べ、省スペースかつ高性能
- パネル工法のため、施工性が高く、短納期施工にも対応
浮床や吸音内装材と組み合わせて使うことで、壁・天井・床すべてで高い遮音効果が得られ、**「静かな検査室」**をより効率よく構築できます。
2. 遮音ドアと開口部処理|漏れを防ぐ基本対策
遮音設計において開口部は弱点になりがちです。
遮音ドアの採用と、ドア周辺・配線孔などの密閉処理によって、必要な遮音性能を確保します。
- STCグレードの遮音ドアを使用
- 開口部には音響シール材や防音パッキンを適切に配置
大掛かりな設計ではありませんが、全体の静けさを支える基本要素です。
3. 吸音材の選定|「反射しない室内」をつくる
検査室内部の反射音や残響音は、測定精度や聴感印象に悪影響を与えます。
適切な吸音処理により、静かで明瞭な音響空間を作ることが必要です。
- 壁や天井に高吸音率(α≧0.99)の吸音材を使用
- 特に**ソノーラテクノロジー株式会社製のBFシリーズ(BFW・BFB・BFP)**は、低域から高域まで安定した吸音性能を発揮
- 反射音補正値(K2値)は2.0dB以下を目安に
吸音設計が整った空間は、被検者にとってもストレスの少ない検査環境となります。
4. 空調と換気|静けさと快適さを両立する設計
どれほど検査室を静音化しても、空調の送風音が耳障りでは本末転倒です。
「静けさと快適性」を同時に成立させる空調設計が必要です。
- 温熱快適性と騒音対策の両立には、音響と空調の連携設計が不可欠です。
5. 測定と検証|暗騒音とK2評価で性能を保証
設計通りに施工しても、実際に静かであるかの検証が必要不可欠です。
医療向けの遮音空間では、以下の測定が推奨されます。
- **暗騒音測定(A特性・1/3オクターブバンド)**による静粛性の実証
- K2補正値測定により、反射音の少ない空間であることを確認
- 測定値:20〜25dB SPL以下、K2 ≦ 2.0 dBが目安
これらの測定データは、設置先の医療機関・監査対応・補助金申請資料としても活用できます。
おわりに|遮音空間は「技術の総合力」でできている
聴力検査室は、単なる「防音空間」ではなく、精密な音響制御が施された医療機能空間です。
構造・吸音・開口・空調・検証の5つを的確に設計・施工することで、検査精度・安全性・快適性をすべて満たす空間が実現します。
インクロジュアでは、ソノーラテクノロジー製品との連携により、高性能・高信頼な検査室の構築をお手伝いしています。
医療現場の「静けさ」が必要なときは、ぜひ私たちにご相談ください。