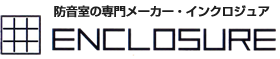病院内に設ける聴力検査室、施工時に注意すべき音環境の落とし穴 ─ 暗騒音・構造伝播・空調ノイズ…見落とされやすいポイントとは ─

はじめに|病院の中は意外と“静かではない”
病院というと「静か」な印象を持つ方も多いかもしれません。
しかし実際には、医療設備や空調機器の常時運転、上下階の動線、屋外騒音など、さまざまな音の影響を受けやすい環境です。
そのため、病院内に**聴力検査室(純音聴力検査室や補聴器適合検査室など)**を設ける際には、音響的な“盲点”に注意が必要です。
この記事では、施工前に押さえておきたい3つの音環境の落とし穴と、それに対する実務的な対策を解説します。
落とし穴①|周囲環境による「暗騒音」の影響
● 見落としがちな「病院内の騒音源」
- 院内搬送用EV(エレベーター)や検体搬送システム
- 空調室外機・配電設備室の振動音
- 外来の待合・受付・スタッフステーションなどの生活音
これらは日中稼働するため、測定時に想定より高い暗騒音値を記録してしまうことがあります。
● 対策ポイント
- 設置場所はEV・機械室・交通動線から離れた区画を優先
- 必要に応じてフロア浮構造や遮音ブースを採用
- 施工後にはA特性+1/3オクターブの実測評価を実施
落とし穴②|構造体を介した「固体伝播音」
● 軽視されやすい建物構造の影響
上階の足音やキャスターの振動音、隣室のベッド移動などが床・壁・梁を通じて伝わることがあります。
これは空気音よりも制御が難しく、事前に検討していないと後からの対処が困難です。
● 対策ポイント
- 壁・床は**質量+絶縁層(浮床など)**の組み合わせで対応
- 吸音材ではなく遮音構造の選定がカギ
- 使用頻度の高い共用部と物理的に離す設計を検討
落とし穴③|空調・換気設備からの「低周波ノイズ」
● 検査中に気になる「耳障りな風の音」
聴力検査室は長時間にわたって閉鎖空間になるため、空調・換気は必須です。
しかし、風切り音・ダクトの共鳴音・ファンの振動音が検査に干渉することも少なくありません。
● 対策ポイント
- 吹出口・吸込口には多孔拡散板や吸音グリルを採用
- ダクトはサイレンサー併用型+曲げ部吸音処理が推奨
- 室内機は防音ボックス化、もしくは別室設置
まとめ|「静かさ」は設計だけでなく“現場対応力”も問われる
病院内での聴力検査室の設置は、計画時の音響設計だけでなく、施工時・運用時の音環境への適応力が成功の鍵を握ります。
特に、施設全体の利用状況や時間帯ごとの騒音特性などをふまえた現場実測とフィードバック対応が重要です。
インクロジュアでは、病院内での暗騒音対策・K2測定・遮音検証など一連の検査体制を整えた上で、最適な検査室設計と施工をご提供しています。
計画段階からの音響相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。