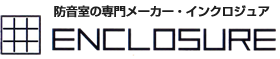静けさの再設計──聴力検査室リニューアルで失敗しないために ─ 限られた条件下で、最大限の遮音性能を引き出すためのポイントとは ─

◆ どうしても“改修”で対応するしかない――そんなときの考え方
施設の構造上、あるいは予算の都合で「新設ではなく既存室の改修で対応したい」というケースは少なくありません。
しかし、聴力検査室に求められる静けさは極めて高く、暗騒音20dB以下という基準をクリアするのは容易ではありません。
本記事では、「どうしても改修で行う場合」に失敗を避けるために押さえておくべきポイントと、最も効果的な音響改善の手順を解説します。
◆ 改修で見落とされやすい、3つの音の落とし穴
① 天井裏・梁を伝う「構造伝播音」
どれだけ高性能な遮音壁を設置しても、建物の構造体そのものが音を伝えるルートになっている場合、
結果的に室内に外部音が侵入してしまいます。
特に多いのが、「天井裏でつながっている配線スペース」や「上下階をつなぐ縦ダクト」からの音漏れです。
▶ 対策ポイント: 施工前に「音の侵入経路」を徹底的に洗い出し、局所遮音(カバーリング)+防振処理を併用する。
② 空調音・風切音の見逃し
聴力検査室では、「空調の“ささやき”レベルの音」も測定に影響します。
既存の空調機器を流用すると、風速が強すぎる・送風音が残る・制御が効かないなどの問題が発生しがちです。
▶ 対策ポイント:
- 風量を制御できる静音タイプに交換
- 消音ダクト・ベントボックス・防振吊りの導入
- 必要であれば外部給排気システムを新設
③ 遮音材の厚み不足と反射対策の不足
既存壁が薄く、遮音材の厚みを確保できないケースでは、遮音性能と吸音性能のバランスが特に重要です。
▶ 対策ポイント:
- 鉛複合ボード+高密度吸音材で薄型かつ高性能を狙う
- 室内側には吸音パネルを設置し、反射音・定在波を抑制
- 床材も浮き床構造にすることで低周波の固体音を軽減可能
◆ 成功率を上げる!改修プロジェクトの進め方
Step 1:改修対象室の暗騒音・反射特性の測定
まずは現地での音響診断を実施。目標性能とのギャップを“数値”で把握する。
Step 2:音の経路別に遮音・防振対策を設計
空調・天井・壁・床、それぞれに合った素材と工法を選定する。
Step 3:計画段階で“性能確認手段”を組み込む
遮音施工後に**性能検証(騒音レベル測定)**を行うことを前提とした設計に。
◆ 音響性能を引き出す製品例(導線パート)
- 薄型高性能遮音パネル(改修用に最適化)
- 防音ドア with ダブルパッキン機構
- 静音ダクトユニット/ベントボックス
- 音場評価ツールによる施工後測定サービス
◆ まとめ:改修でも、音は「科学的に攻める」ことで性能は引き出せる
聴力検査室の音環境づくりは、「音の見える化」から始めることが成功の鍵です。
たとえ新設でなくても、空間特性に合わせて音を“分解して分析”することで、最大限の静けさを引き出すことは可能です。
限られた条件の中でも、患者と検査員が安心できる静音空間を。
インクロジュアは、改修の難しさを知り尽くした設計と製品で、皆様の医療施設をサポートいたします。